|
●面積 約58万平方Km(日本は約38万平方Km)
●人口 約3100万人(日本は約1億3000万人)
●人口密度 53人(日本は331人)
●地理・気候・風土
-ケニア共和国と東京の降水量と平均気温-
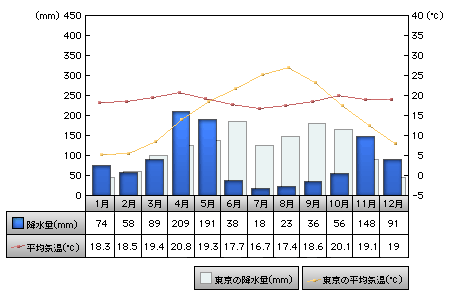
国のほぼ中央を赤道が横切る。海岸地帯から内陸部に入ると,地勢は海抜1,000〜2,000mの草原で,小灌木の高原サバンナ地帯となり,茫漠たる高原がウガンダ国境にまで広がっている。総面積の大半を占める東北辺境地帯は,ほとんど降雨をみない砂漠地帯で,農業地帯は海抜1,000〜2,500mの南部高原地帯である。
気候は海岸地帯と高原地帯で大きなちがいがある。前者は熱帯性気候で7〜9月の乾季をのぞけば高温多湿でしのぎにくいのに対し,後者は年間を通じて気温も低く,空気は乾燥して快適な気候である。季節は大別して雨季と乾季に分かれ,3,4,5の3ヵ月が大雨季,11月が小雨季となっている。
●国のなリたち
この国の海岸地帯は,紀元前からアラビア人,インド人などの往来があって早くから知られていたが,内陸地帯は19世紀半ばまで全く知られていなかった。19世紀後半になって西欧の探検家が次々に入りこみ,中でもイギリス人が多数入植してイギリス風の都市ナイロビを建設,ここを拠点として"ホワイト・ハイランド"とよばれる高原地帯を開発した。1895年にはモンバサとカンパラ(ウガンダの首都)間のウガンダ鉄道建設に着工した。この時35,000人ものインド人を大量移住させたが,これがケニアにおいてインド人が大きな存在となる原因となった。
第二次大戦後,アフリカ大陸に民族意識が次第に高まり,ケニアでも1952年には白人にうばわれた土地の回復を旗印に,キクユ族のテロ分子によるマウマウ団の暴動がおこった。民族運動は1960年代に入ってますますさかんになり,イギリスもついに1963年12月にその独立を認めるに至った。
●政治・経済
1964年7月共和制を採用し,「建国の父」とよばれたジョモ・ケニヤッタ首相が大統領に就任,複雑な国内の部族対立をかかえながらも穏健着実な国づくりを進め,政情はきわめて安定した。しかし,同大統領は78年8月に死去し,モイ副大統領が大統領に就任した。モイ大統領は就任後,近隣諸国との関係改善に努めたが,伝統的に親西欧,親米である。またアフリカ諸国の平和安定に積極的に関与し,ソマリア,ルワンダ,コンゴなどの和平,仲介に熱心である。
労働人口の79%が農民といわれる農業国で,多種多様の農産物を生産する。しかし,対GNP比率は比較的低く,製造工業とサービス産業のウエイトが高くなった。工業は,精油,製粉,繊維,製糖から乾電池,自動車組立など東アフリカでは最も発達している。また,サービス業は,快適な気候,豊富な野生動物のおかげで外国から観光客がおしよせ,観光による外貨収入が大きい。
そうした経過の中で,従来イギリス人,インド人が握っていた経済上の実権はしだいにケニア人の手に移り,穏健な"ケニア化"が進行している。
●社会と文化
ケニアは昔民族移動の中心地だったので,言語,文化から分類すると住民は,バンツー系,ナイロティック系,ナイロ・ハミティック系,ハミティック系となる。宗教は伝統的宗教,イスラム教のほかに,17世紀におけるヨーロッパ人の伝道でキリスト教徒も多い。
●日本との関係
政治的には大きな問題はなく,貿易面では恒常的に日本の出超が続き,この不均衡改善のために,ケニアが一時輸入制限措置をとったこともあったが,円借款の供与で問題は収まった。また,わが国からは専門家や青年海外協力隊員などが派遣され,この国の建設を助けている。
|