

| (1) |
煩雑な計算の処理 |
| 日常生活と数学を結びつけるとき,大きな数や小数など煩雑な計算が出てきます。これらの計算は,時として数学の非本質的な部分の労力を要求します。コンピュータは計算が得意ですから,こうした計算を正確にしかも短時間で実行します。煩雑な計算をコンピュータにまかせることで,生徒にその結果の意味を理解する余裕を与えることができます。煩雑な計算が簡単に短時間にできることを知れば,生徒は同じような計算を繰り返して行うようになり,その中にある傾向や法則などを自分たちで見つけられるようになります。 |
 |
| (2) |
正確な描画機能と関心を高めるアニメーション機能 |
| グラフは点から構成されますが,黒板で作図するときはチョークで走り書きしてしまいがちです。個々の点がどのような意味をもっているか,その集合としてのグラフがどのような形をしているか,さらには基になった関数がどのような性質をもつか,コンピュータの描画機能を使えばステップ・バイ・ステップで確実に理解できます。特に,アニメーションは生徒に大きな関心をもたせる効果があり,動いているというだけでグラフへの取り組み方が変わってきます。ましてや,自分たちがいとも簡単に難しい関数のグラフを描けることは,その後の学習で大きな自信につながります。 |
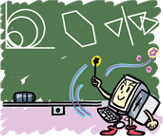 |
| (3) |
コンピュータの作図機能で学習 |
| ノートや黒板に図形を描く場合と比べて,コンピュータによる作図は正確で繰り返しが可能です。また,コンピュータによる作図では,点の位置や角度などを連続的に少しずつ変化させることができます。変化の様子を自由に観察することで,図形のもつ性質を発見して証明するというオープンエンドな学習(注1)や,帰納的な方法で図形の性質を導くという学習が容易になります。そして,自ら課題を見つけ,それを解決する力の育成にもつながります。 |
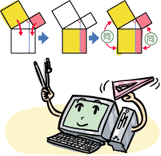 |
 |
| (注1) |
オープンエンドな学習:終わりを決めないことで,たくさんの考え方や答えが作り出せる学習。 |
|
|